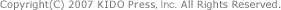土屋 裕介/Yusuke Tsuchiya
“node”
2022年10月8日(土)~ 2022年11月13日(日)
月・火は休廊
「node」、その複数的散乱―土屋裕介の人物像について900℃以下の温度での焼成が繰り返され、人肌のように柔らかな質感を全身に纏う土屋裕介の人物像。近年では、素焼きの後に透明釉や色ガラス等が用いられ、低温ゆえのそれら表面への定着の不完全さが、存在としての虚ろさを私たちに強く印象付けてきた。作品の周到な設計をあえて留保し、己の触覚と視覚にその多くを委ねることで辿り着く、具象と抽象という二つの領域を彷徨い形を成す制作手法は、その特異な人物表現において、意識的に選び取られてきたものだ。つまり、ここ数年の土屋の彫刻制作は、人間という存在の不確かさにその全てが捧げられてきたと断言してよい。
交わりを持つ結節点を示す「node」を、タイトルに掲げる本展において、土屋が目論むのは境界線を有さない「中間の場所」の創出である。それは、複数の固有の対象が内と外の境を溶解させ、曖昧さを保持する「余白」に満たされた場ともいえる。人間の像(イメージ)の集積であり、かつ空虚を内在する土屋の彫刻は、鑑賞者が見つめるその先に過去の記憶や感覚を投影するための「node」となって、無数の他者の視線を脆弱で繊細なその表面に受け止め、佇むことだろう。
そのような作家の意識において、降り積もるように作用し、事物そのものを変性させる要素となる時間もまた欠かせないはずだ。何度も試みられる焼成、あるいは作家の関心から選ばれる古色を帯びた額縁といった制作過程や古物の作品への導入は、人間の身体という内側に「在る」ことを根拠付けることなく、むしろ外部へと開かれうる別の通路を観る者に指し示そうとしている。身体が断片と化すことで、外部空間へと移行、浸透し、「窓」と、さらには「鏡」として機能する額縁に収められた風景と身体が、時間を堆積させたその表層で重なり合う造形性は、内と外の曖昧な領域での様々な相互作用を誘発するのであり、人間という存在の複数的散乱と共振を、その空間に充溢させている。
森啓輔(千葉市美術館学芸員)

“node”
<作家コメント>
記憶の中に溜まった澱を、崩さぬように掬って象る。
柔らかな土は柔らかなままに、瑞々しい光は瑞々しいままに。
象られた身体は断片化し、分解と生成を繰り返しながら、空白を見るための装置として佇んでいる。
均衡を保つために微動し続ける像たちを、星座を描くように繋いだ場に生じた、瘤のような結び目。
そこに「人というもの」が在るような気がしている。
ギャラリーキドプレスでは、土屋裕介の『node』展を開催いたします。土屋裕介の世界観が余すところなく表現された美しい作品、空間をぜひご高覧ください。
<土屋裕介プロフィール>
1985 千葉県生まれ
2009 東京藝術大学美術学部彫刻科 卒業
2011 東京藝術大学大学院美術研究科彫刻専攻 修了
主な個展
2021 「Pale light」(岡の, 東京) 「arium」(gallery Kasper, 神奈川)
2019 「Mirror」(公津の杜コミュニティセンター、ギャラリー海, 千葉・Gallery KIDO Press東京)
2016 「土屋裕介展」(Gallery KIDO Press,東京)
「nowhere」(Gallery KIDO Press,東京)
2015 「土屋裕介展」(公津の杜コミュニティセンター, 千葉)
2014 「know」(Gallery KIDO Press,東京)
2012 「gilding」(Gallery KIDO Press,東京)
2010 「dreamer」(ギャラリーせいほう, 東京)
2009 「your world」(ギャラリー海, 千葉)
主なグループ展/アートフェア
2022 『インクルーシブル・サイト=陶表現の現在』(千葉市美術館、千葉)
2019「おめでとうの春色展」(藝大アートプラザ,東京)
2017 「蒐集衆商」(スパイラルガーデン, 東京)
2016 「3331 アートフェア」(3331アーツ千代田, 東京)
2015 「3331 アートフェア」(3331アーツ千代田, 東京)
2013 「ジ・アートフェアズ・プリュス・ウルトラ」(スパイラルガーデン, 東京)
「大石雪野×土屋裕介 二人の彫刻家」(Gallery KIDO Press,東京)
2012 「Cozy Winter」(DIC川村記念美術館付属ギャラリー,千葉)
2011 「二人の彫刻家 佐藤忠良(銅版画)×土屋裕介(彫刻)」(Gallery KIDO Press,東京)
「プリュス・ジ・アートフェア 2011」(東美アートフォーラム,東京)
「TAMAVIVANTⅡ:ただいま検索中」(多摩美術大学/パルテノン多摩,東京)
「ネオ・ブッディズム」(Gallery KIDO Press,東京)
2010 「第三回ルシャキパル展」(佐倉市立美術館,千葉)
2009 「アートアワードトーキョー丸の内2009」(東京駅行幸地下ギャラリー,東京)
「アートの中のわたし、わたしの中のアート」(からさわクリニック,東京)
その他
2022 アルバム「Beta」(音楽:宮内優里 / アートワーク)
2016 書籍「一〇一教室」(著者:似鳥鶏/装丁)
2012 映画「悪の教典」(監督:三池崇史/作品提供)

“Less Ⅷ”
node, its plural derangements - statues by Yusuke Tsuchiya
Repeatedly fired at temperatures no higher than 900 degrees Celsius, the surfaces of the statues (sculptured human images) produced by Yusuke Tsuchiya are covered all over with a soft texture like that of skin. In recent years, Tsuchiya has applied transparent glaze, colored glass, and other materials after bisque firing. The incomplete fixation of these materials to the surfaces of the sculptures because of the low temperatures left a strong impression of their emptiness as existences on us. Boldly dispensing with a meticulous design for the works, Tsuchiya instead came up with the approach of leaving much to his own senses of touch and sight, and began producing pieces whose appearances wander around the two domains of the concrete and the abstract. He deliberately chose this technique for his unique depiction of human beings. In short, it could be confidently asserted that his production of sculptures over the last few years has been wholly dedicated to the uncertainty and precariousness of human existence.
In this exhibition titled node, in the sense of nodes of connection in networks, Tsuchiya’s intention is to create an “intermediate place” without any border lines. This could also be termed a topos replete with a blankness in which plural individual subjects dissolve the demarcation between inside and outside, and preserve a vagueness. Tsuchiya’ sculptures are agglomerations of human images and also have an immanent emptiness. They serve as nodes for the projection of past memories and feelings before the gaze of their viewers. There they stand, their delicate, sensitive surfaces accepting the stares of countless visitors.
In this outlook of the artist’s, time is another indispensable element that acts like sedimentation and denatures things. The incorporation of the production process and second-hand articles in the form of repeated firings and the antique-looking frames selected by the artist based on his interest are attempts to indicate to viewers that there are no grounds for “being” on the inside = the human body, and that there are, on the contrary, different passages which could open on the outside. By its transformation into a fragment, the body moves into and infiltrates external space. Meanwhile, the landscape and body enclosed in the frames, which function as windows and mirrors, overlap on the uppermost stratum of time’s sedimentation. This plasticity induces various interactions in domains with blurred boundaries between inside and outside, and makes the space overflow with the plural derangements and resonance of the existence that is humanity.
- Keisuke Mori, Curator, Chiba City Museum of Art
Comment by the artist
Scooping up and molding the dregs sedimented in the memory without breaking them.
The soft earth left soft, the vibrant light left vibrant.
The molded body, turned into a fragment, stands as a device for seeing the blankness while going through the cycle of decomposition and formation.
The images continue quivering to maintain their balance, and nodes like protuberances that arose there link them, as if drawing a constellation.
I have the feeling that “something human-like” is there.
We at Gallery KIDO Press are pleased to announce node, an exhibition by Yusuke Tsuchiya. Please come and experience the beautiful works and space completely expressing Tsuchiya’s vision of the world!